清水建設と日本SF作家クラブのコラボレーション企画「建設的な未来」は、これからの社会に起こりうる事柄に対する、よりよい未来の「建設」に向けて、私たちができるかも知れないこと、また、乗り越えた先にあるかも知れない世界をテーマにしたショートショートです。
第2話は門田充宏さんの『理想の小説家』です。お楽しみください。
第2話
理想の小説家
門田 充宏
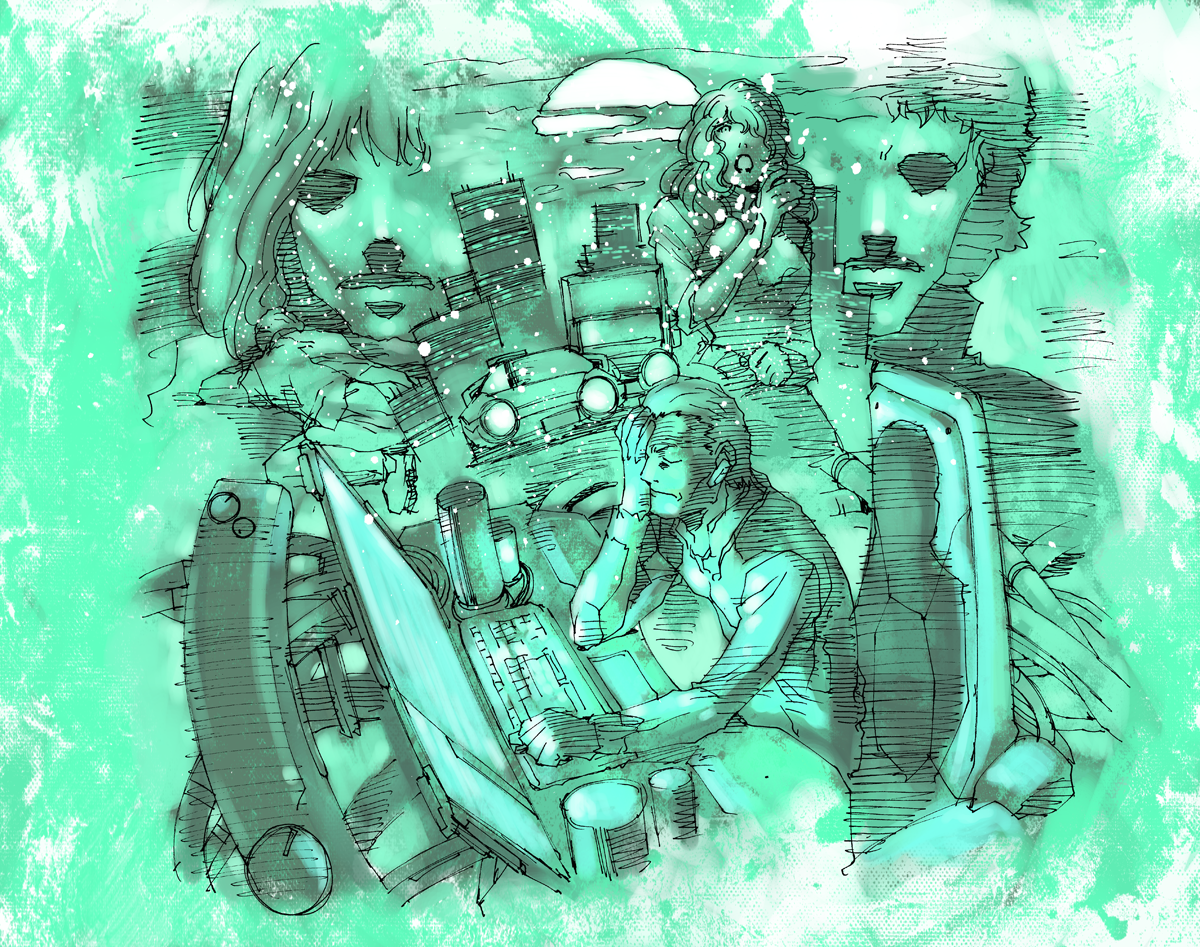
諸君は小説家を目にしたことがあるだろうか?
いや、答えて戴くには及ばない。わざわざ口にしてくれなくても、それがノーであることを俺は良く知っている。
世界には新作小説に対する膨大なニーズがあるというのに、今や小説家は絶滅危惧種だ。新作の出版は絶えて久しく、読者の飢えは増すばかり。
だがそれも今日で終わりだ。なぜならば俺、理想の小説家として誕生したこの俺が、遂に最後のピースを手に入れたからだ。
骨董ものの液晶コンピュータと接続可能な、QWERTYキーボード。
俺は慎重にコンピュータをブートし、言語入力プログラムを起動した。人差し指で慎重にキーボードをタイプすると、期待通りに液晶画面に文字が表示される。
よしっ。
思わず俺は拳を握りしめた。
やはり小説はキーボードで書くに限る。音声入力や脳波入力など論外だ。そんなやり方では小説の魂が欠けてしまう。
いにしえの名小説家は誰もみな同じように、左右の人差し指を使ってポツポツとキーボードを叩き、小説を書き上げたものなのだ。その史実を熟知しているからこそ俺は苦労して、今や骨董品であるキーボードと液晶コンピュータを入手したのである。
だがそれ以外に必要なものは何もない。なにせこの俺は、過去200年間の小説家像を集めて構築された完璧な人造人格を人型ボディにインストールされた、理想の小説家なのだ。そんな俺が遂にキーボードを手に入れた。これで傑作が生まれないわけがあるだろうか?
俺は止めどなく溢れてくるアイディアに物を言わせ、意気揚々と2本指タイプを開始した。
「『——背後に追っ手の存在を感じとり、彼は息を止めた』」
説明から小説を始めるなど愚の骨頂。物語は初めから動いていなければならない。緊迫感のある場面で第一文を始められたことに俺が密かな満足を感じた途端、俺の内耳に人造人格編集者の声が響いた。
〈主人公が死亡した、という意味か? ここで主人公が死亡すると開始早々物語が完了してしまうことになるが〉
「違う、そうじゃない」
編集者は俺の人工脳のサブ領域にインストールされた存在だ。姿は見えないが、音声によってコミュニケーションを取ることができる。俺はどうやら頭が固すぎるらしい担当編集者に向けて、小説のイロハの説明を試みた。
「この場合の『息を止めた』は主人公の緊張感を示す表現に過ぎない。つまり言ってみれば比喩の一種だ」
〈それならば比喩であると注釈するべきだ。その情報が欠落している状態ではほとんどの読者が誤解すると想定される。巻頭の登場人物表によれば主人公は人間だが、人間は呼吸を継続しなければ死亡するというのが一般的な知識だ。従って、恐らく読者の90パーセント以上は、追っ手に迫られた主人公が自死を選んだものだと——〉
「わかった、変更する」
それ以上編集者に文句を言われる前に、俺は文章の修正を決断した。編集者の意見も柔軟に取り込み、そのうえで期待を超えてみせるのが名小説家というものだからだ。
「『彼はいっとき呼吸を堪えた』——これでいいだろう?」
若干ニュアンスが変わった気がするが、許容範囲内だと俺は判断した。いやむしろ文章のリズムが良くなり、加えて時間経過を意識させ、主人公の具体的な息づかいさえも読者に暗黙のうちに訴えかけることさえできているかもしれない。素晴らしい。さすが俺だ。
だが大変残念ながら、編集者のほうはそうは思ってくれなかった。
〈『いっとき』というのは主観に基づくため正確な描写とは言えない。受け手によって解釈の幅が大きく変動する可能性が高い〉
「読者がそれぞれ異なる解釈ができるのは、むしろその小説が優れているということの証左になる」
俺の確固たる信念はしかし、無念にも同意を得ることができなかった。
〈不確定性を喜ばない多数の読者の存在を認識するべきである。細部の状況描写は正確であることが必要だ。任意の解釈の余地は予期せぬ誤解や読者のストレスを生む〉
書く方のストレスはどうなんだと言いたかったが、俺はなんとか堪えた。
確かに俺の、ターゲット読者についての知識は充分とは言えない。一方で人造人格編集者は、俺が過去200年の小説家の情報を所有しているように読者やマーケットについての潤沢な情報を所持している。その編集者にここまで明確にダメ出しされたのだ。ここは実際変更した方が良いのかもしれない、と俺は無理矢理納得することにした。
読者に迎合するのではない。俺は自分に言い聞かせた。わかりやすくするのだ。わかりやすいのは大切だ。
「・・・『彼は3秒間息を止めた』」
果たしてこれでいいのか? と俺が自分でも疑問に思うより早く、編集者の冷徹な声が、俺が全く想定していなかった部分に突っ込んだ。
〈その3秒間を主人公はどうやって計測したのか? 人間にはそこまで厳密な時間測定機能も身体制御機能もない〉
「あああああもおおおおおおおおおお」
俺は反射的に両手をキーボードを叩きつけた。
〈すまないが君の発言内容が理解できない〉
人造人格編集者の冷静な声が俺の内耳に響いた。
過去1世紀で人類の居住区域は伝統的な地域から大きく広がりを見せ、海上、海底、軌道上、そして月面へと広がっていった。当初はそれでも生活というものについての共通認識はある程度維持されていたが、それぞれの居住区域生まれの世代が育ってくるとそういうわけにもいかなくなってきた。
かつては同じ地球上でも、たとえば水はタダで無限だと思っている集団と、最重要戦略資源だと認識している集団のように文化的差異はあった。だが少なくとも物理条件は同じだったし、気象の地域格差はあるにしても概ね共通する知識はあった——たとえば雨は降るし風は吹くし太陽は照りつけるものだった。
だが今やその手の共通認識は存在しない。生活環境も習慣も社会構造も千差万別、たとえば雨という言葉を知らない者も少なくなく、「太陽が昇る」という言葉を聞いて思い浮かべる状況は読者によってまるきり異なる。
容易に想像がつくであろう。これは、小説家にとっては厄介極まりない状況であった。
「『彼女の言葉に振り向くと、彼の目が捉えたのは真っ赤な夕焼けだった。その赤い光が彼の目を——』」
〈その描写では海中都市及び衛星軌道・月面都市の住人には理解できない。『夕焼け』を描写するのであれば、環境についてのより詳細な説明を行うことが必要である〉
そうかもしれない。そうかもしれないが、俺が書いているのはロマンスとサスペンスで味付けしたミステリであって、環境解説の科学読み物ではないのだ。なんでミステリに気象現象の解説パートを組み込まなければいけないのだ。
「『頷いた彼女の瞳からは涙が溢れ出し、頬を伝わって』」
〈地球上・衛星軌道上・月面上で涙が溢れ出たあとの状態が異なるため、重力についての描写を追加する、ないしはその点を考慮した描写に変更することを強く推奨する〉
実在の小説家像の集積から構築されているため、俺の思考や行動や反応はほぼ人間と同じだ。要するにどういうことかと言うと、俺はこの状況に尋常ではないストレスを感じつつあるということだ。念のために言っておくがこれは相当に婉曲的な表現だぞ。
俺の小説は書き始めてから400字詰め原稿用紙(という他に類を見ない特殊なフォーマットが小説執筆においては存在するのだ)でまだ5枚にしか到達していないが、俺が平均27字を書くごとに人造人格編集者は問題点を指摘し修正を提案し、うんざりした俺が対応を保留するごとにやつが作り出す〈あとで追加するべき説明〉〈詳細に行われるべき描写〉のメモは増えていく一方で、そのボリュームは既に俺が記述した文章の8倍に達していた。
